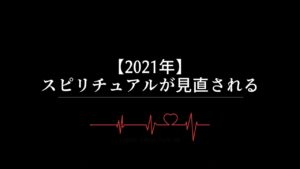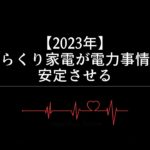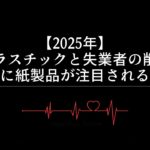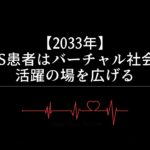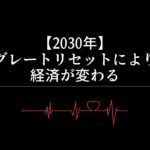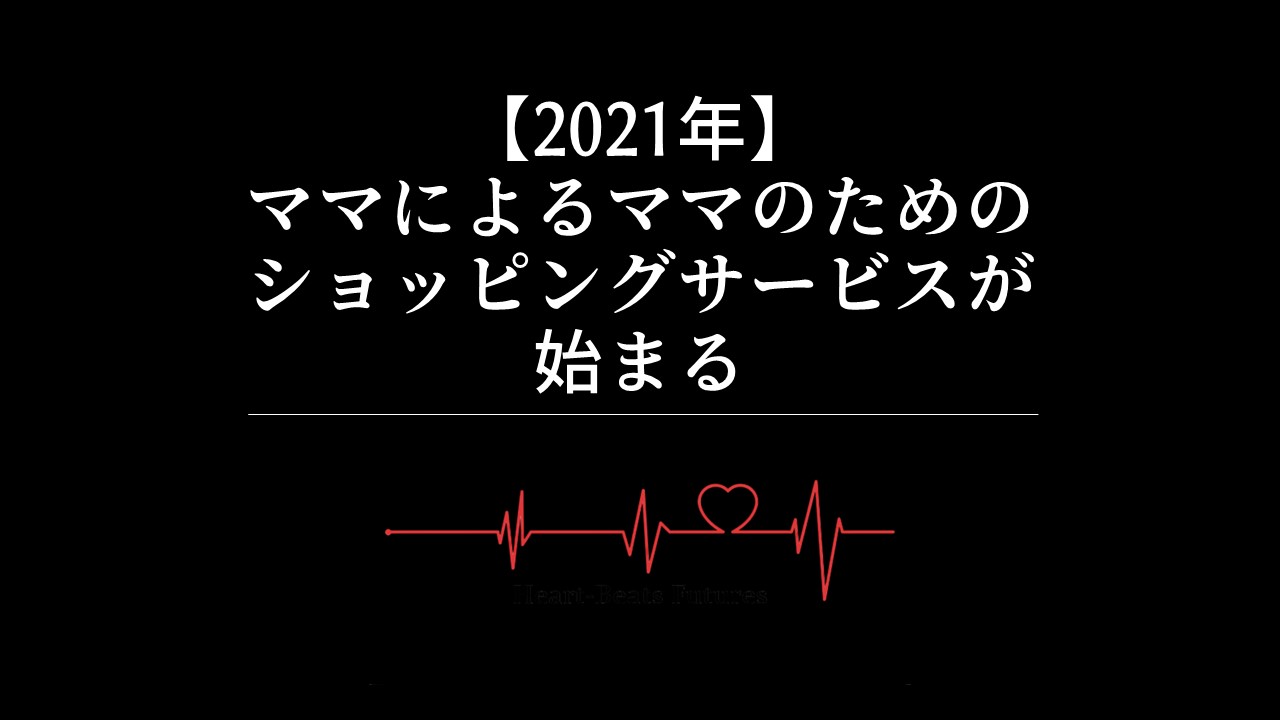
世の中の「ママ」は、とても忙しい。
今でこそ夫婦で家事をする家庭も増えたが、昔は家事・育児などは女性の仕事と言われていたのだ。
もちろん、男性も積極的に家事・育児に参加するべきだと思う。とはいえ、やはり家庭内で、女性は何かとやるべきことがたくさんあるのには変わりない……
特に出産間もない「ママ」は、非常に大変だ。
今回の記事は、そんな「ママ」がもっと活躍できる場を増やすための方法について未来予測をしていこうと思う。
目次
ママにとって活躍の場を増やすサービスが今後増えていく

女性が育児によって、これまで勤めていた会社を退職もしくは休職することは珍しくない。
しかし問題なのは、その後の会社への復帰なのである。
厚生労働省の2019年(令和元年)雇用動向調査によると、期間を定めずに雇われている人や1カ月以上の期間を決めて雇われている人のうち、男性の離職率は13.4%だが、女性の離職率は18.2%となっている。
つまり女性は、「結婚」「出産・育児」「介護・看護」といった理由による離職率が高いのが現状なのだ。
第1子出産前後に女性が仕事を続ける割合は年々高まっているとはいえ、それでも第1子出産を機に離職する女性の割合は46.9%にも上る。
【解決したい課題】
育児しやすい社会を実現する
今回は女性に焦点を当てるが、男性にとっても育児しやすい社会を実現できないものだろうか。
特に女性は、「出産」という人生の大きなイベントだ。精神的にも、休める仕組みや体制を整えていかなければいけないだろう。
最近は助産師不足という問題もある。安心して「お産」できるための未来予測は、【2023年】フリーランスの助産師によって幸せな「お産」を実現する社会にを参考にしてみてほしい。
【そう思ったきっかけは?】
自分自身が出産後の社会復帰に難しさを感じており、どうすればあらゆる状況のママが満足する社会参画ができるのか考えようと思った。
その方法はもちろんひとつではない。ただ、「誰かの役に立っている」「自分は社会に必要な存在だ」と自己肯定できる仕事をなにか持っていた方がいいのではないかと感じている。
それは子育てでもいいし、ボランティアや趣味でもいいと思うけれど、経済活動だったらどのようなアイデアがあるだろうと考えてみた。
【何がそうさせているのか?】
子育て中のママが社会復帰するには、これまでルートが限られていた。
妊娠前から正社員で働き、産休や育休をとって給与と雇用を保証してもらえば、一定の負担軽減になるだろう。
そんなことはない、それでも大変だという人もいるかもしれない。
しかし、夫が転勤族で正社員に就きづらく、知り合いのいない土地で預け先もなく、保育園に入れようにもまず職に就いてからと言われる、そのようなママが少なからずいる。
シングルの場合、さらに状況は過酷だ。
つまり、正社員で福利厚生を受けるルート以外は社会復帰に大小の負荷がかかるというところに問題がある。
そしてルートから外れていると、身内や周囲からなぜ保育園に子どもを預けて働かないのかと言われることがある。
少し前なら、子どもを放って働きに出るなんてかわいそうだと非難されたのに(私の母がそうだった)、時代によって「ママの正解」は変わるようだ。
【既存サービス、取り組みについて】

これまでも、保険や化粧品の営業、「ヤクルト」など子育て中の女性を活用している企業では、ママコミュニティの中で営業したり、保育園を設けるなどしてママワーカーの働きやすい環境がつくられてきた。
(参考:https://www.yakult.co.jp/yakultlady/charm/)
一方、そういった働き方が性に合わないと、起業するママもいる。
ただ、ママ自身がママ向けのビジネスを起業し、大成功する例はまだ少ないと感じる。
それはママ向けビジネスに限ったことではなく起業自体が大変だからでもあるが、子育てと両立させるための労働時間の制限や、利益の出にくい経営をしてしまうことが原因だと考えられる。
そのなかで成功しているママ経営者は、自分と同じママの状況をもっと良くしたいという「仲間の救済」がモチベーションになっているように感じる。
例えば、学生服のリユースショップを経営する株式会社サンクラッドの馬場代表は、自分のママとしての困りごと解決を、全てのママにシェアしようと考えビジネスを展開した。

(参考:https://note.com/kochistartupbase/n/n09037a65fa1d)
課題は、いかに効率よく、いかに利益を出しながら社会貢献ができるかということではないだろうか。
【だからこうした方がいいんじゃないか?】
ママ向けのショッピングビジネスを始める。
ライブコマース(LC)で店頭商品を知り、店舗でじっくり確かめて選んだらオンライン決済して手ぶらで帰る。
商品は当日配送され、ポーター(配達員)とも交流できるサービスだ。運転資金の問題だが、これを福祉事業としてスタート時に大学や行政のサポートを得られないだろうか。
大学は社会実験ができるし、行政は実績ができる。母子手帳にお試し券を同封すれば、認知度も上がるだろう。
また、その後安定して利益を得るには競合しないことが大切だ。
デパートの場合、高額商品はスキルの高いデパート店員に任せ、レビューが求められる商品や入れ替わりの激しい商品に絞ってLCで来店を促す。
そして客が来店しポーターサービスが発生したらデパートから料金をとってサービス提供する。
デパート側の負担はポーター費用のみで販促費は無料なので、初めは出来高制に近い。
徐々にライブコマース経由以外でポーターサービスが増えれば、ポーター側の収益が上がっていくという仕組みだ。
利用者のママにとっては、同じママのポーターが来て少しおしゃべりするだけで気が晴れることもあるだろう。
そしてママワーカー側も、子連れで配達せざるを得なくても理解が得られやすそうだ。
【なぜそう考えるのか?】
社会復帰ができず悩むママに大事なことは、福利厚生を受けているママをうらやむでもなく、社会に不満を言って終わるでもなく、自分の状況下でできる最善のルートを自ら見つけ出すことだ。
持続可能な社会を目指す今、小規模コミュニティの経済活動に着目した。
また、自分と違う状況の人に営業するより、共感しあえる関係性の人の方がビジネスがうまく回ると考えた。
例えば今回の場合は、ママは時に業者となり、時に顧客にもなる。
サービス利用した経験のあるママが子育てに余裕ができたとき、今度は働く側になって新たにママになった人へサービス提供するということだ。
これまでのように競争や激務を生むことなく、相互扶助のように利益が循環していけばいいなと思っている。
どうやって運転資金や利益を安定化させるかが要だが、はじめは大学や行政に頼りながらも、ライブコマースが軌道に乗って税金の補助なしに経営できるようになっていくことが理想である。
20XX年、ママによるママのためのショッピングサービスが始まる

2021年、ママによるママのためのショッピングサービスが始まる
活躍するママが増えることで、女性の社会進出の流れも大きくなるだろう。以前とは違う、「女性中心」の社会も生まれるかもしれない。
子育ても仕事も両立できる、女性が活躍する社会の実現も今後あるのかもしれない……